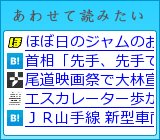上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
今は亡き友の妻 (10)
おれは言葉で響子を攻めながら、同時に、響子の秘処に挿入した指を忙しなく往復させる。響子の中はとても狭く、しかし同時に、中からとどめなく蜜が分泌されはじめており、締め付けのきつさにも関わらず、動きをどんどん激しくしていくことには、なんの支障もなかった。響子の股間はおれの指が動くたびに、じゅっ、じゅっ、と、音を立てて下着を濡らすようになっている。響子の上体も断続的に震え、うっすらと汗をかき、真っ白い肌の表面に光沢を与えはじめていた。時折やけに荒い息のつきかたをするのは、たぶん、ともすれば自分が上げそうになる歓声を懸命に押さえようとした結果だろう。
つまり、響子の身体は充分に反応しはじめていたが、響子の意志はそれを否定し、抑制しようとしているのが、現在の状態だった。
「ねえ」
いつの間にか取り出した三脚で持っていたビデオカメラを固定しながら、冨美子がいった。
「響子ちゃんの身体、きれいでおいしそう。ちょっと味わってもいいかな?」
冨美子の言葉は、文法的には質問の形をとっていたが、文脈的には宣言文に等しい。実際、冨美子はその言葉に響子が反応する間を与えずにすたすたとこちらに歩み寄り、響子の両肩に手をそえて頭を少しさげると、こり、と、歯で響子の乳首を甘噛みしはじめる。
「っんっひゃ!」
と、初めて、響子が鳴いた。
「いい? それとも、痛かった?」
冨美子はいったん響子の乳首から手を放し、頭を上げて響子の耳元に囁く。
「わたし、女性を責めるの初めてだから、加減がちょっと分からないのよね」
冨美子は、「感じるポイントはだいたい分かるけど」、と、付け加えると、そのまま響子の耳の穴の中に尖らせた舌を突っ込み、ねぶる。
液晶の中の響子は、蒼白な顔をして下唇を噛み、なにごとかに堪え忍ぶ表情をしていたが、冨美子が責めはじめるのと同時におれが指の動きを激しくし始めたので、段々、「あっ。あっ。あっ」という低い呟きを漏らすようになっていた。
「響子ちゃん」
下半身を激しく責め立てながら、おれは響子の耳元に囁いた。意図的に、敬称もそれまでの「さん」付けから「ちゃん」付けに変えた。
ちょうど、おれたちが出会った頃、学生時代にそう呼んでいたように。
「良樹がいるときなら、これは浮気だろう。でも、もう、良樹はいないんだ。どこにも。操を守る、なんて今時はやらないし、良樹も、響子ちゃんが家に閉じこもっている状態は、悦ばないと思う」
言い終えて、さらに指の動きを速くし、響子のうなじを丹念に舐める。
それまで抑えがちだった響子の声が、堰を切ったように大きくなりはじめた。
冨美子は、しばらく響子の乳房を手と口で弄んでいたが、徐々に頭を下のほうに下げていく。
「おいおい」
冨美子が舌で響子の臍あたりを責めるようになった頃、おれは冨美子に声をかけた。
「そんなに下がったら、おれの手と当たっちゃうじゃないか」
「だったらあんたがその手をどかしなさいよ」
わたしは響子ちゃん自身を味わいたいのー、と、冨美子は、拗ねたような声でいった。
「でも、だんだん良くなってきたところで指抜いちゃうと、響子ちゃんに悪いだろ」
「だったらこうしましょう」
冨美子は、それまで開くまいと力を込めてい閉じていた響子の膝をあっさりと開き、片足の脛を自分の肩にのせる。
「この体勢なら、背中側からも、腰の下から手を入れられるでしょ」
名案だったので、おれはいったん響子の中に入れていた指を抜き、お尻の側から響子の濡れて重くなった下着をかき分けて再度指を侵入させた。充分迅速に動いたつもりだったが、おれが指を抜いたとき、響子は、明らかに不満げなため息をもらした。
おれの指が下から響子の襞をかき分けて濡れた内部を掻き回し、その上の敏感な突起を下着の上から冨美子が舐めはじめると、もやは響子には受け続ける快感を隠す術も余裕もなく、おれの頭を脇に抱えて凄い力で締め付けながら背筋をそらし、断続的に全身をふるわせながら、「あー。あー。あー。」と、喚きはじめた。
おそらく、響子自身はすでに忘我の境地にあり、自分の狂態を自覚していないに違いない。
響子の絶頂は、すぐそこに近づいているようだった。
[
つづき]
【
目次】