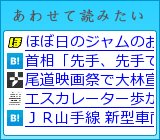第六章 「血と技」(256)
「……そんで、話しを元に戻すけど、グラサンのねーちゃんは結局のところ、どうするんだ? ん?」
三島が、豚汁を啜ってから荒野に尋ねる。
「だから、それは茅の意向次第だって……」
荒野は、それまで一方的に聞き役に回っていた茅に話しを振ると、三島は小声で、
「……もうすっかり、尻に敷かれてやんの……」
と呟く。
『……一度、無理矢理口をこじ開けて、昨日の極辛カレーのルゥ、たっぷりと詰め込んでやるかな……』
と、荒野は考えたが、とりあえず他の者たちの手前、聞こえないふりをして聞き流した。昨日、茅がやけになって作ったカレーは、結局、全員なんとか一皿を完食するのがやっとだったので、残りはタッパーに入れて冷凍庫に放り込んでいる。
捨ててもよかったが、食べ物を粗末にすることに抵抗があったし、それに、取っておけば何かの罰ゲームの時にでも、使いようはあるだろう。
「静流との繋ぎを強化すると……荒野は嬉しい?」
茅は、すぐに返答する代わりに、荒野に尋ねかえす。
「嬉しい、ってよりも……野呂本家とのパイプが太くなれば、やりやすくなるってのは、あるかな……」
荒野は、考えながら、慎重に返答した。
「……前にもいった通り、例の悪餓鬼どもの追跡調査に信頼できる術者を確保したいところだけど……それ、現状だと、しばらくは難しいわけで……その点、野呂本家が紹介してくれる人なら、そういうの、安心して任せられるだろうし……」
もともと、単独での動くことを好む野呂は、そうした漠然とした手がかりしかない状況からの地道で根気のいる追跡調査、というのを得意とする血族だった。
「……ヴィにもやって貰っているけど、姉崎と野呂とでは、同じ調査でも方法論が違うし、それに、一刻でも早く向こうの状況を把握しておきたいから、人手は多ければ多いほど、いい……」
……さらにいうと、姉崎の捜索班と野呂のそれとで競争意識が発生すれば、荒野にとっては理想的な状態になる……と、思ったが、流石にこの考えは、この場では口にできない。それに、シルヴィと静流なら、その程度のことはいわずとも察しがつく筈だ、とも、思った。
「……ひ、姫様……」
静流が茅に話しかける。
一族の関係者の間では、茅のことを「姫」ないしは、「加納の姫」と呼称することが多かった。
「……そ、その件について、協力することは、な、なにも異存はないのです。
の、野呂に、優秀な加納本家の血を入れる代償と思えば、や、安いものなのです……」
静流がわざわざ、荒野や茅にとってのメリットを説明しなかったのは、恩着せがましい印象を持たせたくはないためだろう、と、荒野は予想する。それと、あんまり静流が荒野を希求していることを強調して、茅の嫉妬心に火をつけるのを、警戒して……ということも、あったのかも知れないが。
いずれにせよ、静流が「野呂本家の一員」として判断し、交渉しよう、という姿勢をみせていることは、確かだった。
そうであれば……仮に、この先、野呂が荒野に協力するとしたら、先に手を着けている姉崎への対抗上、それなりの腕利きを揃えてくることが、予想できた。
『……おれみたいな、ガキ一人でも……』
それなりに、交渉材料にはなるもんんだな……と、荒野は、他人事のように思った。
荒野自身の実力が買われたわけではなく、荒野の血筋を信用して……という取引だから、荒野の思考は冷めきっている。種馬扱いされて喜べるほど、荒野は鈍感ではなかった。
「……いいと思うの……」
茅は、しばらく何かを考え込んだ後、あっさりと頷いた。
「茅と荒野に、デメリットはない取引のようだし……」
そのあと、茅は声を出さずに口を動かす。その口唇の動きを、荒野は、「……他の女に触れると、それだけ茅にもさわってもらえるし……」と読んだ。
……シルヴィとそうなった時の、二倍から三倍の約束は、ここまで有効になるのだろうか……と、荒野は思い、内心で慄然とした。
「……あ、ありがとう、ございます……」
静流は、茅に向かって顔を向け、頭を下げる。
年下である茅を公然と立てるあたり、静流もそれなりの器だな……という印象を、荒野は持った。
「……わ、わたしも、ここでの生活を、な、長続きさせたいので……ほ、本家の肝いりで、腕の利くものを、そ、揃えるのです……」
荒野と静流がそういう関係を持つ、というのは、野呂本家を動かすいい口実にはなるか……と、荒野は思い、それから、静流の申し出そのものが、公然と荒野へ助力するための口実なのではないか、と、疑問を持った。もっとも、この疑問については、静流を問いつめてもとぼけられるだけだろう、とも思ったが。
いずれにせよ、荒野にしてみれば、相手が完全に体勢を整える前に尻尾を掴みたい、という強い希望があったので、ここであえて静流に乗せられるのが、得策なのだ。
静流を抱くことで、野呂の一流の術者たちの協力を得られるのであれば、それは荒野にとっても、かなり「お得」な取引というべきであり、感謝はしても文句をいう筋合いはないのだった。
「……そうすると……五人の女の間を、ローテーションでやりまくるわけか……」
三島は、ぐるりとその間にいる人たちを見渡して、そういった。
「……うひひっ。
役得だな、荒野……」
「……いや……。
それなりに、大変だと思いますけど……」
三島にそういわれた荒野は、珍しく少したじろいだ。
考えてみれば……荒野は、そもそも、まともに異性とつき合った経験があまりない。表面的には、合意が取れているとはいえ、これだけ癖の強い女性たちと同時に関係を結んで、うまくバランスをとって、継続的につきあい続けることができるかどうか……はなはだ、心許なかった。
『……今度、隣りの香也君に、うまくやるコツでも聞いておこう……』
と、荒野は思った。
彼のことだから、「うまくやろう」と考えたり身構えたりすることなく、自然体で捌いている……という可能性が強かったので、尋ねたとしても、身のある助言は得られないかも知れないが……。
「……パツキンだろ、グラサンだろ、ロリ双子だろ、そんでもって、本命の茅だ……」
荒野がそんなことを考えている間にも、三島は言葉を続ける。
「……よりどりみどりのやりたい放題っ!
男の本懐だなっ! 荒野っ!」
……この人は……人の気も、知らないで……と、荒野は思う。
「……本懐は、いいですけど……」
荒野は、その場で、深々と頭をさげた。
「おれ、正直、女性の扱い方とか、そういうのよくわからないっすけど、何か失礼なことしたら、なるべくなおしますから、すぐに指摘してください……」
ただでさえ、不確定要素が多く、綱渡りに近い関係なのだ。
下手にでて協力を引き出す方が得策だし、自分の気も楽だ、と、荒野は考える。
「……ん?」
三島が、何かに気づいた顔をした。
「……こ、これは……全員年上の、おねーさんハーレムなのではないかっ!」
三島がそういうと、荒野以外の全員が、顔を見合わせる。
「……当然、年上……」
シルヴィが、片手をあげた。
「……お、同じく、年上なのです……」
静流が、片手をあげる。
「「……外見に反して、年上です……」」
酒見姉妹が、声を揃えた。
「……実は、年上なの……」
茅も、片手をあげる。
「……お前さん……。
これで、おとーと属性だったんだなぁ……」
三島が、何故か感心した声をあげる。
荒野は「属性」という語彙に込められた意味が理解できなかったので、なんとも返答のしようがなかった。

[
つづき]
【
目次】
有名ブログランキング↓作品単位のランキングです。よろしければどうぞ。
newvel ranking HONなび