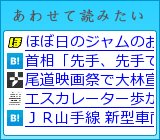第六章 「血と技」(331)
「わははははっ。ひっさびさの登場ぉっ!
なんちて」
いきなり、三島百合香は車の前で胸を張って哄笑し、意味不明のことをわめいた。茅も、他の三人も特に驚いた様子がないのは、この人物の奇矯な言動に慣れているからだった。
「送迎ぐらい、まかせろ。
ってぇか、もっと早くにいえってーの。
それでなくとも最近、出番が減る一方なんだから……」
ぶつくさいいながら、三島は愛用の小型国産車のドアを空け、四人を中に招き入れる。
「……今まで、羽生さんに送って貰ったり、自分の足で歩いていったりしてたんだって?
ひとこと、いってくれりゃあいいのに……。
こっちだって、あの佐久間とかいうスタンド使いたちには興味あるんだから……」
テン、ガク、ノリが後部座席に、茅が助手席に座ったことを確認して、三島は車を発進させる。三島の運転は無難なもので、とりたてて危なっかしいところもない、いわゆる「安全運転」だった。
「……先生、質問っ!」
後部座席にいたガクが、しゅたっと片手を上げて質問する。
「スタンド使いって、なんですか?」
「うかつにそういう質問をすると……」
茅が、ぽつりと忠告する。
「……ネット書店で全巻一括買いして送られてくるの。日本のマンガは、冊数が多いの……」
「……うーん……。
具体的に説明してのもいいんだが……それじゃあ、面白くないからなぁ……。
あっ。羽生さんなら、持っていそうだな、あれ……。
でなければ、堺のうちにいくといいぞ。あいつ、おやじさんだかが結構なマンガ好きで、どっさり古いマンガがコレクションされているっていうし……」
「……ようするに、マンガの話しなんですね……」
テンが、悟ったような顔をして、頷いた。
「おう。
JOJOっていう大河マンガだ。これからシリーズ全作一気読みしようとしたら、確実に一日は潰せるぞ、あれは……」
三島は、ハンドルを握りながら、そんなことをうそぶく。
「……それより、お前らは、今、なにやってんだ?
茅は、この間の隠し芸以上のことも、できるようになったのか?
食卓を丸ごと見えなくして隠し芸、なんちて」
「わずか数日では、そんなに変わらないの」
助手席の茅は、静かな口調で答えた。
「ただ、観察した結果を推論で補っていたところに、系統だった理論の裏付けがとれて、補強された部分は、あるの」
「……そーか、そーか。
見よう見真似と山勘に頼っていたのを、正統派のメソッドで辿りなおしている……ってところか……」
三島は、軽い口調で相槌をうつ。
……態度は軽いけど、これで、理解力がないわけでもないんだよなあ……と、観察していたテンは、三島について、そう思う。
「……あれで現象も、説明するところはしっかりとせつめいするからね……」
ガクがそう補足すれば、
「態度は、相変わらず偉そうなんだけどね……」
ノリも、そういって頷く。
「まあ……百聞は、一見にしかずってやつだな」
三島はそういって、うっすらと笑った。
「実際にみてみりゃ、どんなもんか、いやでもわかるだろう……」
「……ありゃ?」
三島が車の窓を開け、顔を出すと、出迎えに来ていた二宮舎人は、間の抜けた声を上げた。
「……先生……。
今夜は、あんたが見学か……」
「顔を出すなりあんた呼ばわりたぁ、ご挨拶だな」
三島も、にやにやと笑いながら応じる。
「羽生さんの時には、ちゃんとお客さん扱いされたって聞いてるぞ……」
「先生。
そもそも、あんたは長老に雇われて新種の面倒を見ている人で、無関係の一般人である羽生さんとは、立場が違うでしょう……」
舎人と三島とは、以前、狩野家の台所で一緒に料理を作ったり、レピシを交換したりしていた。
二人の性格的な相性もあり、軽口を応酬する程度には、打ち解けていた。
舎人に誘導されて車を庭に入れると、玄関の前に酒見姉妹が肩を並べて待機しており、三島や茅たちが家の前の立つと、
「「……いらっしゃいませ」」
と、声を揃えて頭を下げた。
「藁葺き屋根の田舎屋敷に、双子のメイド服……」
ミスマッチというか、シュールというか……などと、三島はぶつくさいっている。
「で……何かと思えば……」
三島は、現象と茅、テン、ガク、ノリたちに講習を目の当たりにして、勝手に想像していた光景とのギャップに、戸惑いを隠せなかった。
「……やっていることは、発声練習かよ……」
現象が他の四人と向き合い、最初に声を出す。
複雑な抑揚で、音の高低差も、激しい。
歌……というには、とうてい、意味のある歌詞には聞こえない。唸り……というか、音。それが「歌」であるとすれば、明らかに呪歌であろう。
その声を唱えている時、現象は、その音を発するための気管としてのみ、存在している。現象の体中が一つの音を絞り出すような「管」と化しているような、印象がある。
むしろ、現象の身体を通して、別の世界からの風が、ごうごうと吹き抜けている……というような、印象が、ある。
時折、現象が喉の奥から絞り出す音が、ヒトの家長音域を超えて聞こえなくなったりするが、肌は、周囲の空気がビリビリと振動していることを、三島に認識させる。
そうした複雑怪奇な「音」を、現象を追うようにして、茅、テン、ガク、ノリの四人が、真似て、自分の喉から絞り出そうとしている。
が、あの器用な茅からして、まだ完全に成功してはいないようだ……と、三島は、感じる。
現象が出す「音」と、他の四人が出している「音」では……部外者の三島にとっても、明らかに、違ったものに思える……。
「でも……みなさん、飲み込みが早いですよ……」
三島が不満そうにしているのを感じたのか、佐久間梢が、そう囁く。
「普通なら……ここまでたどり着けたとしても、多くの落伍者を出した上で、何ヶ月もかかります。
みなさんは、未だ、一人の落伍者も出していないし、わずか数日でここまで来ているわけですから……新種って、本当にすごいんですね……」
「……落伍者?」
三島は、梢に短く聞き返す。
「ええ。
適性がない人は、どんどん落とされます。
だから、真正の佐久間は、常に少数なんです」
梢は、頷く。
「加納の姫様に牽引されているのが大きいのか……適性的には劣るガクさんやノリさんも、その分、努力して懸命に追いつこうとしています」
三島は、再び特殊な「声」を発している茅たち四人に視線を戻す。
その表情をみても……確かに、茅やテンに比べれば、ガクやノリは顔中に汗をびっしりと浮かべて、あまり余裕があるようには思えない。
「この歌……お聞きの通り、複雑で……記憶力に劣る人は、かなりの反復練習をしなければ、ここまではいかないんですが……」
「こいつらは……体力と根性は、人一倍、あるからな……」
三島はそういって、頷いた。
おそらく……まず、テンが修得したものを、昼間の間に時間をかけて、他の二人、テンとノリの練習させ、身体に染み込ませているのだろう。

[
つづき]
【
目次】
有名ブログランキング↓作品単位のランキングです。よろしければどうぞ。
HONなび