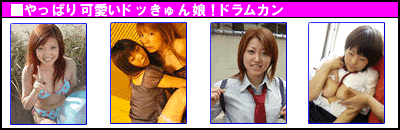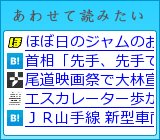上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
隣りの酔いどれおねぇさん (9)
「なんなら、一緒に入ります?」
加々見さんは、そんな軽口がたたけるほどには、ほぐれてきた。いい傾向だ。
「さっきシャワーを浴びましたし、加々見さんと一緒にはいると中でいろいろやって、疲れてマッサージどころではなくなりそうなので、今回はご遠慮します」
丁重にお断りして、脱衣室から辞して、物置にしているロフトをごそごそと物色する。
少し前に出て行った彼女は割と熱しやすく冷めやすい人で、いろいろな物を買ってきては、一度か二度、使っただけで後は放置される、みたいなアイテムが、結構残っていた。
今回役に立ちそうなのは、バスローブ、マッサージ・オイル、アロマテラピー用の香料入りキャンドル、とかいったところか。それらをもって出て、バスローブは入浴中の加々見さんに「出たら、これ着てください」といって、脱衣所に置いてくる。
キッチンの椅子にどっかりと腰を下ろし、残っていたコーヒーを啜りつつ、一休み。すっかり冷え切っているが、酔いさましにはなる。
「わぁ。本格的」
数十分して、頭にタオルを巻き、バスローブを纏った加々見さんは、テーブルの上のマッサージ・オイルの瓶とキャンドルをみて、いった。半ば呆れているのだと思う。風呂上がりの加々見さんは、上気して血色の増した肌に艶がでているようで、普通に立っているだけでも、色っぽかった。
「全て、出て行った彼女の置きみやげです。どれも、ほとんど使った覚えがありませんが」
そういって、セミダブルのベッドが置いてあるだけの部屋に案内する。っていうか、ダイニングキッチンではいほうの部屋、ってだけのことなんだが。
「それじゃあ、失礼して」
加々見さんは、そういうと、なんの躊躇もせず、するり、とバスローブを脱いだ。下に、下着一枚つけていなかったので、全裸、だった。黒々とした陰毛の茂みも全て、露わになる。基本的には痩せ型。でも乳房だけは大きく前に張り出している。
「なに、こんな傷物のおばさんの裸、みて面白い? 全身マッサージ、してくれるんでしょ?」
たしかに、下腹部に大きな手術の後が残っているけど……。
「いえ、綺麗だったんで、見とれていただけです」
素直にそう答えると、照れ隠しなのか、加々見さんは「やーねー」といいつつ、ぺちん、と、ぼくの肩を軽くはたいた。
裸になった加々見さんがベッドの上に俯けに寝そべったので、ぼくはライターでキャンドルに火をつけ、部屋の照明を落とす。リラクゼーション効果がある、とかいうふれこみの、抹香臭い香りが薄暗くなった室内に充満しはじめ、なんだかアヤしい雰囲気になった。ぼくはマッサージ。オイルの瓶をあけ、加々見さんの背中に少し垂らし、掌で、背中全体に薄く延ばす。そして、肩、上腕、肩胛骨の辺りから初めて、徐々に下の方へと、順々に加々見さんの背中をも揉みほぐしていく。
多少、真似事をやったことがあるとはいっても、ぼくは本職でもないし、きちんとした方法を学んだわけでもない。それでも、時間をかけて丁寧に揉みほぐしていくと、加々見さんは、時折、気持ちよさそうな、艶めいた声を上げてくれた。そういう反応が面白くて、ぼくはさらに丁寧に、力を込めて加々見さんの肉をほぐしていく。
湯上がりの加々見さんの肌は、上気して温かくなっていたが、ぼくの体温のほうも、慣れない作業、それも、意外に肉体を酷使する重労働のおかげで、すぐに汗だくになった。額に浮かんだ汗が加々見さんの体に垂れないように、時折、そっと拭いながら、ぼくはさらに作業に没頭していく……。
「はい。もう、充分。後ろは、もういいわ」
我を忘れて、加々見さんの背中に取り付いているぼくに、加々見さんはそういって、体を起こす。
「すっごく、気持ちよかった。そのまま寝ちゃいそうになった。同じような調子で。今度は、前の方をお願い。それとも、……」
全てを晒して、今度は仰向けに寝そべった加々見さんを前に、しばらく躊躇していたぼくの目を正面から覗き込みながら、加々見さんはいった。悪戯っ子のような、笑顔を浮かべている。
「……マッサージよりも気持ちのいいことまで、してくれるの?」
そういうようなわけで、それ以降のマッサージは、ほとんど前技にちかいものになった。
[
つづき]
【
目次】
↓作品単位のランキングです。よろしかったらどうぞ。
NEWVEL ranking HONなび ranking


隣りの酔いどれおねぇさん (8)
「上着は脱いでもらった方がいいですね」
といいつつ、壁際にあるスタンドからハンガーをひとつとり、加々見さんに手渡す。加々見さんは腰を浮かせて上着を脱いでハンガーにかけ、それをぼくのほうに返す。加々見さんから手渡されたハンガーをスタンドにひっかけ、いよいよ加々見さんの背中に向き直り、肩に手をかける。
ブラウスの薄い布地越しに、加々見さんの体温を感じた。
「それでは、いきます」
「お願いします」
相変わらず、背筋を伸ばしたままの加々見さんが答える。
……うーん。まだ硬いよなぁ……。
最初から力を込める、ということはしなかった。
人差し指と中指、それに親指の三本の指にだけ、軽く力をいれて、加々見さんの首の付け根、両脇部分を摘む。他の指は添えているだけ、のような感じで、軽く振動を与えるように、動かす。さほど力を入れているわけでもないのに、
「はっ。んっ」
と、加々見さんは、すぐに色っぽい吐息を漏らしはじめた。
そして、加々見さんの首が、ほんのすこし、前後に揺らぐようになる。加々見さんの首が前のほうに振れると、加々見さんのうなじが丸見えになって、その白さが目にまぶしい。こうしてみると、加々見さん、色白だよな。
まだまだ、ごく表層の部分を軽くほぐしているだけでもこれほど気持ちよさそうにしているとは……。加々見さん、予想通り、かなり凝っていると見た。
それでも焦らず、じっくり、力は振動を与える程度に抑え、ぼくは揉む範囲を徐々に広げていく。
首の根本からはじめて、徐々に外側に向かうにつれ、指の下に感じる加々見さんの温度が微妙に上昇していく。うなじとか、頬とか、加々見さんの肌の後ろから見える部分の、透けるような白い地に、ほんのりと朱色がさしはじめる。
「もう少し、力を込めていいですか?」
「お願い!」
加々見さんは、いつもとの平静さとは打ってかわって、かなり強い語調で即答した。
「もっと強くして!」
……うーん。じらしていたつもりはないのだが、そんなに凝っていたのか……。
たしかに、指に感じる加々見さんの肉の感触は硬質で、容易にほぐれない、つまり、長期戦になる、ということはすぐにみてとれた。だから、ことさらじっくりとウォーミングアップを施したわけだが、そのウォーミングアップの段階で、これほど反応するとなると、本格的に揉みはじめたら、いったいどうなってしまうのだろう?
とりあえず、リクエストに応える形で、ギアをもう一段アップさせる。
とはいっても、それまで皮膚あたりまでしか刺激しないようしにしていたところを、もう少し下層の、皮下脂肪に届く程度に力を込めた、というくらいの、本当にささやかに変化をつけただけなのだが……加々見さんの反応の変化は、覿面だった。
ぼくが肩胛骨の上の、特に硬い感触を感じる部分に、親指に少し力を入れて、をぎゅっと押し当てただけで、加々見さんは、
「んはぁ」
と、大きく息を吐いて、上体をのけぞらせて硬直した。
「あ。痛かったですか?」
「いい! すごく、気持ちいい!」
加々見さんは、感極まった、という感じの声でいった。
「君、うますぎ!」
そういって、加々見さんは、肩にのせているぼくの手の上に、自分の掌を重ねる。
……いや、喜んで貰えるのは嬉しいけど……。
そういう反応は、こういうところではなく、ベッドの上でこそ、して欲しい。そういう思いも、ふと頭をよぎる。
それに、ぼくがうまいのではなく、加々見さんの凝りが酷すぎたのだと思う。ストレスの原因には、事欠かないようだったし。
「……続けます」
それから十五分くらい、ぼくは加々見さんの肩を揉み続け、加々見さんは大げさなほど反応し続けた。もし声だけを聞いている人がいたら、絶対二人で別のことをやっていると勘違いしただろう。それほど、加々見さんは、ことある毎に嬌声をあげ、痙攣し、悶絶した。いや、比喩ではなく、実際にそんな感じ。
その証拠に、十五分くらいして、ぼくの手が痙攣して続行不能になった頃には、加々見さんは全身に汗をかき、きれいにセットされていた髪もほつれさせ、ブラウスを肌に貼り付け、肩で息をしていた。
フォーマルな恰好をした女性が、こういう状態になっていると、妙に艶めかしい。
「さ。お風呂に入ってきてください」
ぼくは、肘をテールブルにつけ、前傾姿勢で荒い息をしている加々見さんにいった。
「……お風呂……」
俯いていた加々見さんがのろのろと顔をあげて、ぼくを見上げる。ほつれた髪の間からかいま見える、加々見さんの目は、とろん、と、蕩けたような感じだった。
「もう、お湯、張ってますから。ゆっくりとお風呂で暖まってきたら、今度は全身をマッサージしましょう」
ぼくが続けて、「出て行った彼女が置いていった、マッサージオイルがあるんですよ」と、囁くと、加々見さんの顔が、ぱぁあ、っという擬音がするのではないか、と、思うほどに、鮮やかに、輝いた。
[
つづき]
【
目次】
↓作品単位のランキングです。よろしかったらどうぞ。
NEWVEL ranking HONなび ranking

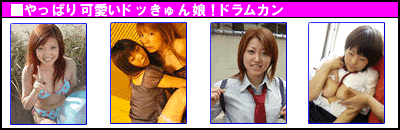
隣りの酔いどれおねぇさん (7)
淹れたばかりのコーヒーを嚥下する。室内の気温は、暖房を必要とするほどでもないが、少し肌寒い。そんな中、熱い液体が食道を徐々に降りていく感触を感じると、体の中心から安堵感が広がっていくような気がする。
今ぼくの目の前にいる女性は、普段ならあまり公言しないような、自分の境遇を語り終え、笑みを作ろうとして、それに成功していない。なんとも奇妙な、アンバランスな表情を、蒼白な顔に浮かべている。
ピンと伸ばした背筋と、その凍り付いたような表情とが……彼女の置かれている、否、彼女が自分自身を追い込んでいる場所の、居心地の悪さを、そのまま物語っているようだった。
基本的に、真面目な、真面目すぎるくらいの、人なのだろう。
なにもかもを、きっちりと、完璧に、それができなければ、無難にこなそうとして、たいていの場合、それができてしまう程の能力も、持ち合わせている。
でも、表面的な事務処理を機械的にこなすのと、心理的なジレンマを内面的に整理するのとは全く別の話しで……例えば、「離婚」とかに必要な手続きを推進するための気力や能力と、自分自身が、そこにまで至った過程に対して納得しているのか、ということは、全くの別の問題で……。
多分、彼女は、常に「よい子」であろうとし、「よい子」であり続ける能力もあり、……それゆえ、自分の内面の、消化不良の、鬱屈した心理と向き合うのが、後回しになり、どんどん鬱屈やストレスを溜めていくのだろう……。
……本当に、こんな時くらい、泣き喚いて、取り乱しでもすれば、多少は楽になるのに……。
コーヒーを飲みながら、ぼくは、今目の前に居る女性に、いったいなにができるのか、ということを考えていた。彼女は、ほとんど面識のないぼくにかなり立ち入ったことを話す所まで追いつめられて/自分を追いつめているわけで……そもそも、記憶をなくすほど泥酔したり、ぶしつけに、ぼくのような他人に、そのような事柄を語ったりすること自体、彼女が無意識に、一種の安全弁を求めている、ということだろうし……。
「加々見さん」
ぼくが声をかけると、もちろん、意識して柔らかい声を作ったわけだけど、それでも、硬直して何事か考え事をしていた加々見さんは、ぼくの声を聞くと、ビクリ、と、体全体を震わせて、反応した。
「よかったら、その、肩を揉ませてくれませんか?」
「え? あ。ああ」
ぼくのその申し出が、唐突、かつ、よほど予想外だったのか、加々見さんは、数秒、目をぱちくりさせていた。
「ええと……その、別にかまいません、けど……」
まあ、いきなりこんな事をいわれても、普通は驚くわな。でも、メンタルの前にフィジカル。体の方をほぐしたほうが、効率がいい。加々見さんは、加々見さんの体は、良いが覚めてから、緊張してガチガチだった。
「では、その前に、バスタブにお湯を張ってきます」
ぼくはことさらゆっくりと立ち上がり、浴室のほうに向かう。といっても、狭いマンションの中、すぐにいって帰ってくるわけだけど。で、加々見さんの後ろに立って、肩に手をかける前に、いう。
「いや。前の同居人には、よくマッサージしていたんですけどね。ぼちぼち一月くらい、他人の体を揉んでいないので、できれば、練習台になってくださると、ありがたいです。ブランクが空きすぎると、腕が鈍りますから」
「ええ。ああ」
加々見さんの声に、少し、柔らかさが戻ってきた。
「そういうことなら、どうぞ。ご自由に。泊めさせていただく身ですし」
「それでは、今から肩を揉ませていただきます。が、続けて熱いお湯にゆっくり浸かって暖まってから、全身のマッサージを行うと効果的ですので、是非、そうすることをお薦めします」
「……はい。おっしゃる通りに。でも、あの……」
ぼくが加々見さんの肩に手をかけるのと、加々見さんがそう言葉を継ぐのとは、ほとんど同時だった。
「……その同居人だった方のこと、お聞きしてもよろしいでしょうか?」
「つい先頃、ぼくに愛想尽かして出て行きました」
加々見さんほどドラマチックな展開があるわけでもないし、別に隠し立てするほどのことでもない。
[
つづき]
【
目次】
↓作品単位のランキングです。よろしかったらどうぞ。
NEWVEL ranking HONなび ranking
隣りの酔いどれおねぇさん (6)
コーヒーの香りが満ちていく中、加々見さんは、
「……今日、別れた夫に会ってきたんです」
と、語りはじめた。
加々見さんとその人とは、職場で出会った。結婚してから、二人で共同経営という形で、小さいながらも事務所を構えた。何年かして、仕事の方が軌道に乗り始めた矢先、加々見さんの体調を崩し、念のため、病院にいってみると意外に大病で、そのまま何ヶ月か入院。退院したら、相手には新しい女ができていて、しかも、妊娠までしていた……。
そんな顛末を、加々見さんは淡々と、ほとんど声の抑揚をつけずに語り続けた。
よくある話し、といってしまえばそれまでなのだろうが、当事者にしてみれば、かなり大変なことだったのだろう。
ほとんど面識のない、ぼくのような男に語ったのも、相談とか愚痴とかではなく、一通りのことを他人にしゃべるだけしゃべって、なにかしら踏ん切りをつけたいのではないか。
加々見さんのしゃべりぶりは、はなしの内容を考えたら、むしろ怖いくらいに平静で、その平静さというのが、語られる内容が彼女にとって既に「過去のはなし」になっているからなのか、それとも、ことさら平静に振る舞わねば、話している内に自分がどうしようもないほど取り乱してしまう、ということを自覚しているからなのか……。そのどちらとも、判断しかねた。
その、どちらとも、なのかも、知れないが。
「今日は、分社化の正式な手続きとか、彼とか会計士さんとかを交えて詳細を煮詰めてきたんです。その後、出資してくれることになっている古い知り合いと会って、飲んで……」
淹れたばかりのコーヒーを、自分用のマグカップと来客用のカップとに注ぎ、来客用のカップを加々見さんの前に置いた以外、ぼくは、相槌もうたずに、黙って聞いていた。
加々見さんはコーヒーには手を着けず、相変わらず背筋をシャンと伸ばし、視線を空中のどこか一点に擬っと据えたまま、はなしを続ける。
一緒に飲みに行った加々見さんの古い知り合いも、比較的最近ご主人と死別したばかりで、ついこの間まではかなり沈み込んでいたこと。でも、今日久々にあったら、かなり元気になっていて、男と別れたばかりの女同士、にぎやかにおしゃべりしながらかなり飲み歩いたこと。久々に記憶をなくすほど飲み、気がついたらマンションの前でぼくに話しかけられていたこと……。
そんなことをはなし続ける加々見さんの血の気のない、真っ白な横顔を眺めつつ、ときおり静かにコーヒーを飲みながら、ぼくは黙って聞き続けた。
「こんなとき、女ってダメですね」
最後にそう締めくくったとき、それまで表情を消していた加々見さんは、笑おうとしているようだった。
「お酒に飲まれて、あなたにもこんなにご迷惑をおかけして……。
わたしって……」
……弱いですね……。
そう続ける加々見さんの横顔を眺めながら、ぼくは、
──……こんなときぐらい、素直に泣けばいいのに……。
と、そう思った。
[
つづき]
【
目次】
↓作品単位のランキングです。よろしかったらどうぞ。
NEWVEL ranking HONなび ranking



隣の酔いどれおねぇさん (5)
加々美さんをリビングに案内した後、先刻宣言した通り、ぼくはさっさと風呂場に向かう。
加々美さんにも当座の着替えにスウェットとポロシャツぐらい出しておくべきだったかな、とか思いつつも、どろどろになったスーツとワイシャツを手早く脱ぎ、ざっとシャワーを浴びる。なにぶん、不快な匂いと感触を一刻でも早くなんとかしたかったので、気が急いていた。
熱いシャワーが心地よい。
最低限の汚れを洗い流しただけで、風呂場から脱衣所に移動し、バスタオルでざっと体を拭い、部屋着として置きっぱなしにしてあるものを身につける。汚れたスーツとワイシャツは、しばらく思案した末、とりあえず、洗濯機に放り込んでおく。後で捨てるかも知れないが。不幸中の幸いか、スーツは何年か着古したものだったので、あまり惜しくもなかった。
バスタオルを首にかけてリビングに戻ると、ピンと背筋を伸ばし、緊張した面もちの加々見さんが座っていた。そして、ぼくの顔をみるなり、立ち上がり、
「ごめんなさい!」
と、深々と頭を下げた。顔色はまだ青白いけど、酔いはかなり醒めたらしい。ぼくがシャワーを浴びている間に、メイクも直しているようだった。
「いやいや。お気になさらず」
ぼくもなるべく鷹揚に構えて返したつもりだったが、そうした擬態が成功したていたかどうかは、いささか心許ない。
「それより、風呂、空きましたよ。良かったら、どうぞ。シャワーだけでも。
それとも、お茶でもいれましょうか?」
どんな経緯であれ、招きいれた以上はお客である。
「あ。わたしがやります。コーヒーでいいですね?」
加々美さんは跳ねるような動作で顔を上げると、こちらが制止する暇も与えず、緊張した、かくかくという動作で、コーヒーメーカーをセットしに向かう。
「あ。水と豆は冷蔵庫に」
仮にもお客さんなのだから、遠慮してもらおうかな、とも思わないでもなかったが、せっかく張り切っているわけだし、狭いキッチンであまり面識のない人ともみ合うことの滑稽さを考えて、結局やってもらうことにした。加々美さんは、割合に馴れた手つきでコーヒーメーカーをセットする。
ぽこぽこという、挽いたコーヒー豆にドリップする音を聞きながら、向き合って黙り込んでいるのもなんなので、
「それで、鍵のほうは見つかりましたか?」
と、訊ねてみる。
「いや、すいません。やっぱりなかったです。どこかに忘れてきっちゃったみたいでして……」
彼女は深々とため息をついた。
「……駄目ですねえ、わたし……普段はこんな、悪酔いするまで飲まないのに……」
「いや……まあ……。そういう気分になるときだってありますよ……」
年上の女性、それも、あまり面識のない、かなりきれい目な人と、二人っきりで正面向き合って、しみじみとそんな会話を交わすのも、滅多にできない経験ではある。まあ、なんといって慰めればいいのか、会話の糸口はなかなかつかめそうにはないのだが。
「お気になさらず。
こんなところでよければ、一晩くらいは泊まっていって構いませんので」
「……はい……そうさせていただけると、助かります」
うつむき加減の加々美さんは、消え入りそうな声でそう応えた。
この辺、結構なんにもない場所で、もよりの駅まで十キロ以上ある上、コンビニさえまばらである。かろうじて、少し離れたところにファミレスがあるくらいで、外泊場所となると、かなり離れたところにしかない。
不便な分、床面積に比べて、家賃も安いわけだが。車をもっているか、この近くに職場があるかしないと、あまり住む気になれないような立地条件だった。
二人とも言葉の接ぎ穂がみつからず、ポコポコとコーヒーのドリップする音だけが、部屋の中に響いた。
[
つづき]
【
目次】
↓作品単位のランキングです。よろしかったらどうぞ。
NEWVEL ranking HONなび ranking